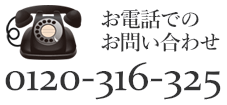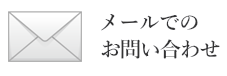突然解雇通告を受けた、残業代が支払われない、などの労働問題のご相談は弁護士対応・埼玉県所沢市・所沢駅西口徒歩6分の埼玉さくら法律事務所へ
TEL. 0120-316-325
〒359-1122埼玉県所沢市寿町3−4
解雇について
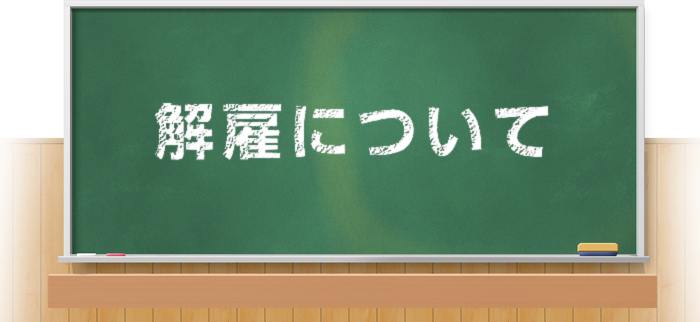
1、労働契約の終了原因
労働契約には、1.期間の定めのあるもの と、2.期間の定めのないものがあります。
1、期間の定めのあるもの
期間の定めのある労働契約は、期間の満了により終了するのが原則です。ただし、期間満了後も引き続き労働契約が存続する「更新」というのがあります。使用者から労働者に対して、「更新しません」と通知することを「雇止め」といいます。
「雇止め」の場合でも常に労働契約の終了が認められるわけではありません。
詳しくは、「雇止めについて」のページをご覧ください。
「雇止め」の場合でも常に労働契約の終了が認められるわけではありません。
詳しくは、「雇止めについて」のページをご覧ください。
2、期間の定めのないもの
期間の定めのない労働契約は、当事者の意思表示によって終了します。労働者側からの意思表示を「辞職」といい、使用者側からの意思表示を「解雇」といいます。
2、解雇の種類
解雇には、以下のような種類があります。
1、普通解雇
通常、就業規則には、解雇事由を定めた規定が置かれますが、当該解雇事由に当たるとして解雇をするのが普通解雇です。
2、整理解雇
使用者が経営不振などの経営上の理由により人員削減の手段として行う解雇を整理解雇といいます。
3、懲戒解雇
使用者が、労働者の服務規律違反等に対して行う懲戒処分のうち、最も重い処分が懲戒解雇です。
3、解雇の制限
解雇というのは、労働者の生活に重大な影響を与えるので、無制約になされるものではなく、以下のように色々な制限がなされています。
1、手続的・時期的制限
(1)産前産後休業・業務災害の場合の解雇制限
労働者が業務上の負傷や疾病による療養のために休業する期間及びその後30日間、産前産後休業の期間及びその後30日間は、原則として解雇をすることができません。
これらの期間に解雇されてしまっては、安心して休業ができませんし、再就職のための活動も困難になってしまうため、このような制限があります。
これらの期間に解雇されてしまっては、安心して休業ができませんし、再就職のための活動も困難になってしまうため、このような制限があります。
(2)解雇予告
使用者は、原則として、解雇をするには、少なくとも30日前に予告をしなければならず、それをしない場合には、予告手当(30日分以上の賃金)を支払わなければなりません。労働者に時間的余裕を与え、生活への影響を少なくするためです。
2、解雇理由の制限
(1)法令による制限
国籍・信条の差別による解雇、女性であることを理由とした解雇、育児・介護休業の取得を理由とした解雇などは、法令によって禁止されています。
(2)解雇権濫用法理
解雇については、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。解雇というのは、前述のように、労働者の生活に重大な影響を与えるので、簡単には認めず、いわば最終手段として認めましょうというのが、この規定の意味です。これを「解雇権濫用法理」といいます。解雇の理由としては、「能力不足」「適格性が欠ける」などが多いと思いますが、裁判所は労働者に有利な事情を考慮し、簡単には解雇を認めません。解雇ではなく、他の手段(配転等)で対処できるのではないかといった事情を考慮します。
違法解雇
解雇が違法の場合、解雇は無効となります。よって、違法解雇の場合、労働者は、依然として労働契約が存在し、労働者としての地位にあることを主張していくことになります。また、違法解雇がなされた後、使用者は給料を支払っていないと思いますが、「違法解雇」という使用者の責任で労働者が就労できていないので、この場合、労働者が現実に就労していなくても、給料が発生し続けます。この給料のことを「バックペイ」と呼んだりします。よって、「バックペイ」の支払いも求めていくことになります。
以上のように、違法解雇がなされた場合、労働者は、依然として労働契約が存続していることを主張することになりますが、実際には、戻りづらいということもあるかと思います。その場合には、使用者が解決金を支払うことによって、労働契約を終了させるという和解をすることもあります。
埼玉さくら法律事務所
〒359-1122
埼玉県所沢市寿町3−4
※所沢駅西口徒歩6分/駐車場有り
TEL 0120-316-325
埼玉県所沢市寿町3−4
※所沢駅西口徒歩6分/駐車場有り
TEL 0120-316-325